こんにちは。まいにち読解 第2回です。
毎日、朝7時に配信します。
今日は抜き出し問題ですが、答えに至るまでの過程をしっかりと意識して取り組んでみましょう。テーマも頻出の「環境問題」です。
第2回「行き過ぎた環境対策」
現代社会において、地球環境の保全は人類共通の重要な課題であることに議論の余地はない。気候変動や生物多様性の損失といった問題に対処するため、私たちは積極的に環境対策を推進している。しかし、その対策の中には、目的を追求するあまり現実的な社会生活や経済活動との間で摩擦を生じさせたり、かえって新たな問題を引き起こしたりする「行き過ぎた」側面が見受けられる。
まず、「経済活動との摩擦」という問題がある。二酸化炭素排出量を極端に削減しようとする施策は、製造業や運輸業といった基幹産業に大きなコスト負担を強いることがある。そのコストが製品価格に転嫁されれば、消費者の負担が増加し、生活水準の低下を招きかねない。また、開発途上国においては、厳格すぎる環境規制が、貧困からの脱却を目指す経済発展の妨げとなるケースも指摘されている。環境対策は、社会全体の持続可能性を見失っては本末転倒である。
次に、「手段の目的化」という現象も無視できない。環境に配慮した製品やサービスを選ぶ「グリーン消費」が推奨される中で、企業が環境保護を単なるイメージ戦略(グリーンウォッシング)として利用する事例が増えている。また、再生可能エネルギーの導入を急ぐあまり、その施設建設のために貴重な森林を伐採したり、大量の廃棄物を生み出す技術に依存したりするといった、「環境対策」と「環境破壊」が表裏一体となる矛盾も発生している。真の環境対策とは、目に見える効果だけでなく、ライフサイクル全体を通じて環境負荷を低減することを目指すべきである。
さらに、対策が「個人の自由や選択を過度に制限する」という側面もある。特定の資源や製品の使用を禁止したり、個人のライフスタイルにまで細かく規制を設けたりすることは、人々の抵抗感や反発を招き、結果として対策の実効性を損なうことになりかねない。環境対策を成功させるためには、国民一人ひとりが納得し、自発的に行動を変えることが不可欠である。強制的な手段に頼るのではなく、技術革新やインセンティブ(動機付け)を通じて、環境に優しい行動が経済的・精神的に報われるような社会構造を構築することが求められる。
環境対策は、理想と現実のバランスを取る「トレードオフ」の関係性の中で進める必要がある。単なる理想論に終始したり、短期的な成果に固執したりするのではなく、社会全体への影響を多角的に評価し、経済成長、社会の安定、そして環境保護の三者を統合する「賢明な持続可能性」の追求こそが、私たちに課された真の課題だと言えるだろう。
【問】傍線部「ライフサイクル全体を通じて環境負荷を低減すること」と同様の意味の表現を、文章中から十五字以内で抜き出しなさい。
【解き方】
解き方を表示
①問われていることの確認
同様の意味を探す・・・言いかえの問題。
→いきなり探しに行くのではなく、まず自分なりに傍線部の意味を把握する(=傍線部から出発する)。
②傍線部の意味を考える
「ライフサイクル全体を通じて環境負荷を低減すること」
・「ライフサイクル」とは?→ライフ=生活? サイクル=循環?
→単純な話ではなさそう=長期的なもの?
・「環境負荷を低減」→そのままの意味。
③傍線部の周辺(=関係)から意味をつかむ
・前「真の環境対策とは」→傍線部=真の環境対策。
・前「目に見える効果だけでなく」→傍線部は、「目に見える効果(環境対策)と対比関係にある。
・後「~を目指すべき」→傍線部の内容は、「目指すべき」もの。
④ここまでを頭に入れつつ、言いかえを探す
・次の段落「環境に優しい行動」?
→「ライフサイクル全体」の要素を含むか・・・?
・最終段落「理想と現実のバランス」?
→理想と現実のバランスの中で環境対策を進めるのであって、「理想と現実のバランス=環境対策」ではない。
→「社会全体への影響を~」=「ライフサイクル全体」?
→「~を追求」=「目指す」の言いかえ?
【解答】
解答を表示
「賢明な持続可能性」
今日も「言いかえ」の問題でした。今後扱いますが、理由説明などの問題も、ベースとなる考え方は「言いかえ」です。しっかりとマスターしましょう。
質問があれば、お気軽にコメントください。

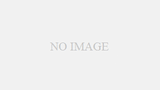
感想・質問はこちら